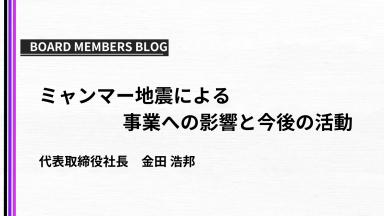世界情勢の不安定化、労働政策の転換、そしてAIや自動運転といった技術革新——。企業を取り巻く環境は、これまで以上に複雑で、変化のスピードも加速しています。こうした時代において、私たちは「人材をどう育て、どう活かすか」という問いに真剣に向き合っています。今回は、当社が今取り組んでいる人材戦略と事業展開について、率直にお伝えしたいと思います。
不確かな時代に、確かな備えを
最近のニュースを見ていて、特に気になっているのは自民党の動向です。世界情勢が不安定な中で、日本が今後どんな立ち位置を取っていくのか。これは、企業を経営する立場として、どうしても注目せざるを得ません。
外国人労働者の受け入れについても、今後の政策次第で大きく変わる可能性があります。新しい政権がどんな方針を打ち出すのかによって、企業の人材戦略にも影響が出てきます。もし受け入れに慎重な姿勢を取れば、人手不足の解消は難しくなりますし、受け入れスキームの再編を進めたからといって、すぐに不正やトラブルが減るとも限りません。現状を維持するのか、一度立ち止まって制度を整えるのか――その判断が、今後の社会の流れを左右すると思って見ています。
そして、何よりも怖いのは「戦争」というリスクです。どんなに事業を頑張っても、国と国の衝突によるカントリーリスクには、私たちの力が及びません。積み上げてきた努力や信頼が、一瞬で失われる可能性があるのです。だからこそ、政治や国際情勢には常に関心を持ち、備えを怠らないようにしています。
当社では、これまで注力してきたミャンマーにおけるリスク対応にも取り組んでいます。例えば、タイに移住しているミャンマー人材に職場をどう提供するか、日本への受け入れ体制をどう整えるか、さらには開発拠点をタイにも作る可能性も含めて、さまざまな選択肢を検討しています。
特に、IT分野では、ミャンマー人材を中心に100名以上のエンジニアが活躍しています。日本の大手企業からの開発案件も多く、ミャンマー国内で頑張っている人たちがたくさんいます。最近では、日本国内での採用に向けた動きも出てきており、彼らのキャリアをどう育てていくか、そして当社のビジネスとしてどう組み立てるかについて、今まさに真剣に向き合うべきタイミングだと感じています。
変化の先に、私たちの次の仕事がある

日本市場が少しずつ縮小していく中で、私たち企業には、海外展開や新しい領域への挑戦がますます求められています。国内では、宿泊業への人材派遣を強化しています。社員登用を希望する企業も出てきています。これは従来の取り組みの延長線上にありますが、経験豊富なメンバーに新しい役割を担ってもらうスキームづくりも、現在進めています。そして宿泊業への人材提供を、さらに加速させることが大きなテーマです。
また、1年半後には倉庫業が特定技能制度の対象分野に新たに追加される予定です。これに向けて、どんな企業とパートナーシップを組み、どのように展開していくか、今から準備を進めています。制度が整えば、長期的かつ安定的な雇用が可能になります。
コプログループではすでに倉庫を保有しており、ミャンマー人材が現場で活躍しています。その中で成功事例も生まれており、これを他の倉庫業にも展開していくことが、今後の戦略のひとつです。グループの強みを活かしながら、サービスの幅を広げていきたいと考えています。
加えて、各地で自動運転の実証実験が進んでいることにも注目しています。当社では、外国人トラックドライバーの採用を進めています。人材不足の解消に向けて、支援技術がどこまで活用できるのか。人が必要な領域と、技術で代替できる領域の見極めが重要になってきています。
学び続ける力が、企業の力になる
これまでJavaなどの実務経験を積んできたエンジニアたちの仕事の内容は、今後大きく変わっていくでしょう。AIがプログラムを生成するようになれば、チェックや前後の作業は残るものの、作業量は圧倒的に減ります。そのとき、今まで真面目に努力してきたメンバーをどう活かすか、次の役割を担ってもらうにはどうすればいいのかといったことが、私たちにとって非常に大きなテーマです。
一方で、技術の進化とは逆行するように、最近ではCOBOLエンジニアへの引き合いも増えています。保有する既存システムの維持・移行においてその重要性が再認識される一方、日本国内で対応できる技術者が減少し海外人材に白羽の矢が立っています。しかし、そうしたプロジェクトが完了した後、COBOLエンジニアたちが次にどんなフィールドで活躍できるのか、そこまでを見据えた支援が必要だと感じます。
AIやクラウドの進化によって、技術の進化スピードは一段と速くなっています。だからこそ、技術だけでなく「人として働く力」を育てることが、企業の持続的な成長に直結すると考えています。そして、その教育環境をどう整えるかが大きな課題です。
派遣や出向で働いている社員は、業務時間のすべてが現場の管轄下にあります。業務外で「勉強しよう」と言っても、労働基準法の制約、労働時間の考え方や働き方の価値観の変化からそうも言いづらくなりました。私たちの世代なら、仕事が終わった後にテレビを見る時間を使って「勉強しようぜ」という空気がありました。でも今は、それが難しい。
それでも、会社によっては、優秀な人材が自分の将来を見据えて資格を取ったり、学び続けたりしています。当社でも、そうした機運をもっと育てていきたい。個人の意識と企業の教育姿勢の両方が問われていると思います。

海外の若者たちは、学びへのモチベーションが高いです。ですが、初めてミャンマーに行った頃と比べると、少しずつその意欲が下がってきているようにも感じます。満たされると楽しいことに目が向くのは、日本もミャンマーも同じです。
企業が人を育てるということは、社員一人ひとりが「自分の未来を描ける環境」をつくること。そして、変化の時代にこそ、学びの場を絶やさないこと。それが私たちの責任であり、今後の人材教育の鍵になると感じています。
代表取締役社長 金田 浩邦